「楽天リンクを1個貼るだけでもPR表記って必要なの?」
「他の人やってないのに…」
正直、ルンも最初はそう思ってました。
「うちのブログなんてまだアクセスもほとんどないし、大丈夫でしょ」と軽く考えて、PR表記なくアフィリエイト広告を貼り付けていました。

PR表記をしたら、読まれない気もしますよね。
でも、調べていくうちに気づいたんです。
信頼され息の長いブロガーさんほど、きちんとルールを守っているということに。
この記事では、初心者がやりがちなステマの落とし穴と、安全に発信を続けるためのポイントをわかりやすくお伝えします。
目次
ステマとは?
ステルスマーケティングの定義
ステルスマーケティング(ステマ)とは、報酬や提供を受けたのに、それを明示しないまま宣伝する行為です。
「買ってよかった!」の一言でも、それが収益につながるリンク付きなら、広告であることを示す義務があると考える時代になりました。
個人でも気をつけるべきなの?

2023年の法改正で、よりステマのルールが厳格化されました。
- 読者をだますような表現はNG
- 景品表示法や広告ガイドラインの対象拡大
- 媒体を問わず、ブログ・SNS・YouTubeなども対象
✅ 「PVが少ないから大丈夫」は通用しません!
楽天リンク1本でもPR表記は必要?
「広告」はすべて対象
はい、必要です。
たとえ楽天アフィリエイトリンクを1本だけ貼っている記事でも、収益が発生する可能性があるならPR表記は必須です。
「みんなやってないから…」という理由でスルーしていると、知らないうちに規約違反になることも。
誰が見てるかわからない
「他の人もやってないし…」→ ASPや広告主は見ています。
読者の通報やライバルのチェック、広告主の監査で発覚する例も多く、炎上や提携解除につながることもあります。
✅ アマゾンアソシエイトやグーグルアドセンスなどとも提携していきたい人は、ステマへの意識を強く持っていた方がよいですね。
PR表記しないことの逆効果
読者は「正直さ」を求める
今の時代、「PRって書いてある=ちゃんとした発信者」という認識が定着しつつあります。
信頼を失う
むしろ、何も書いていない記事の方が読者に不信感を与えるケースも。
✅ 正直に書くことで、信頼されやすくなります。
初心者がやりがちな5つの落とし穴
1. 広告リンクにPR表記なし
リンクの近くか記事冒頭に「この記事には広告が含まれます」と明記しましょう。
2. 「個人的に使ってます」実は提供品
提供を受けた場合は「提供を受けました」と明記する必要があります。
また実際に使用していない商品やサービスを、【体験談】として書くのもNGです。
3. 途中からいきなり広告リンク
長文記事ではリンクの前にも再度「ここから広告リンクになります」と書くのが安心です。
4. 「これを使えば必ず!」などの誇張表現
客観的なデータや体験談にとどめましょう。保証はNGです。
さらに、健康食品や化粧品、サプリなどを紹介する場合には、薬機法(旧・薬事法)にも注意が必要です。
5. 「ASP経由なら安心」の思い込み
ASP経由のリンクも広告に変わりなし。
(ステマへの意識が薄い広告主もいるので)発信者が責任を持ってPR表記をする必要があります。
アクセス数は関係ない
信頼=ブログ継続の土台
ブログをはじめたばかりの頃こそ、「正直であること」「信頼されること」が1番の武器になります。
記事を量産した後に過去の記事を見返して、PR表記を一つひとつ追加していく作業は想像以上に大変です。
だからこそ、初心者のうちからステマへの意識を持っておくことが、本当に大切だとルンは感じました。
- PR表記をつける勇気
- 透明性のある発信
- 自分も読者も守る配慮
たったひと手間で、自分のブログは長く続く土台になります。
そのことを肝に銘じて、「誰も見てないからいいや」ではなく、「誰が見ても安心な発信」を心がけていきたいと思います!
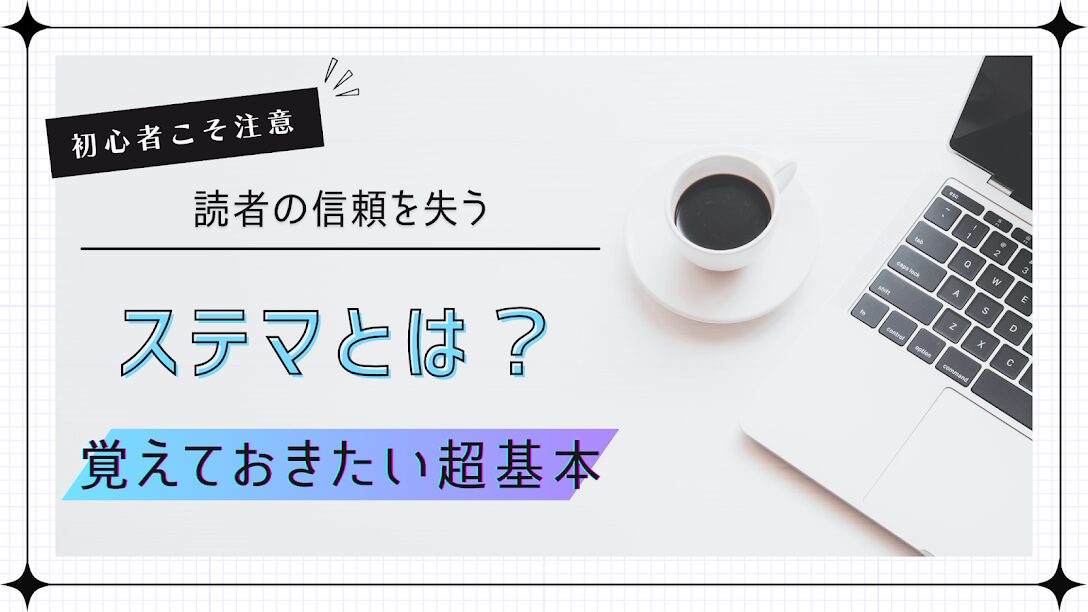
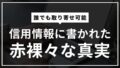

コメント