裁判を傍聴していると、聞き慣れない言葉がたくさん出てきます。
少しだけ意味を知っておくだけで、内容の理解がぐんと深まります。
初めての方でも読みやすいように、よく出てくる用語をやさしくまとめました。

あいうえお順になっています。
目次
- 裁判用語集
- 疑わしきは罰せず(うたがわしきは ばっせず)
- 冤罪(えんざい)
- 開廷表(かいていひょう)
- 家庭裁判所(かていさいばんしょ)
- 簡易裁判所(かんい さいばんしょ)
- 起訴(きそ)と不起訴(ふきそ)
- 禁錮(きんこ)
- 刑事裁判(けいじさいばん)
- 刑務官(けいむかん)
- 嫌疑(けんぎ)
- 検察官(けんさつかん)
- 控訴(こうそ)
- 高等裁判所(こうとうさいばんしょ)
- 口頭弁論(こうとうべんろん)
- 公判前整理(こうはんまえ せいり)
- 拘留(こうりゅう)
- 罪状(ざいじょう)
- 罪状認否(ざいじょうにんぴ)
- 裁判員(さいばんいん)
- 裁判官(さいばんかん)
- 示談(じだん)
- 実刑(じっけい)
- 執行猶予(しっこうゆうよ)
- 釈放(しゃくほう)
- 収監(しゅうかん)
- 上告(じょうこく)
- 証拠調べ(しょうこしらべ)
- 証拠不十分(しょうこ ふじゅうぶん)
- 証人尋問(しょうにんじんもん)
- 書記官(しょきかん)
- 書類送検(しょるいそうけん)
- 心神喪失(しんしんそうしつ)
- 精神鑑定(せいしんかんてい)
- 責任能力(せきにんのうりょく)
- 前科(ぜんか)
- 宣誓(せんせい)
- 地方裁判所(ちほうさいばんしょ)
- 調書(ちょうしょ)
- 陪審員(ばいしんいん)
- 初公判(はつこうはん)
- 判決(はんけつ)
- 被告人(ひこくにん)
- 弁護人(べんごにん)
- 傍聴人(ぼうちょうにん)
- 保釈(ほしゃく)
- 民事裁判(みんじさいばん)
- 無罪(むざい)
- 無実(むじつ)
- 黙秘権(もくひけん)
- 留置(りゅうち)
- 累犯(るいはん)
- 論告求刑(ろんこくきゅうけい)
- 和解(わかい)
裁判用語集
疑わしきは罰せず(うたがわしきは ばっせず)
「罪があるかどうかハッキリしないなら、むやみに罰を与えてはいけない」という考え方です。
裁判では、証拠が不十分なときは無罪になることがあります。
「疑わしきは被告人の利益に」とも言います。
冤罪(えんざい)
無実なのに罪をかぶせられてしまうことです。
まちがった捜査や証言などが原因で、無実の人が有罪になることもあります。
開廷表(かいていひょう)
その日にどんな裁判があるかをまとめた予定表です。
札幌地裁では紙に印刷して掲示されますが、東京地裁などはタブレットが導入されています。
家庭裁判所(かていさいばんしょ)
離婚・親権・少年事件など、家庭に関わる問題を扱う裁判所です。
通称「家裁(かさい)」
少年事件の「非公開の裁判」もここで行われます。
簡易裁判所(かんい さいばんしょ)
比較的軽い事件や、少額のお金のトラブルなどを扱う裁判所です。
交通違反や民事のトラブルなどが多く、1人の裁判官で行われます。
起訴(きそ)と不起訴(ふきそ)
検察が「裁判で争うべき」と判断すると起訴、「必要なし」と判断すると不起訴になります。
不起訴になると裁判は行われません。
ただし不起訴になっても「前歴(ぜんれき)」は残ります。
禁錮(きんこ)
刑の一種で、刑務所に入るけれど作業義務がない刑です。
現在は懲役と統合され「拘禁刑」という言葉に変わってきています。
刑事裁判(けいじさいばん)
人にけがをさせたり、物を盗んだりなど、法律に反した行為をした人を裁く裁判です。
加害者には弁護士、国(検察官)が被害者の立場で登場します。
刑務官(けいむかん)
刑務所で、受刑者の生活を管理したり、指導したりする国家公務員です。
法務省に所属していて、刑を安全に執行するための大切な役割を担っています。
被告人が身柄を拘束された状態で裁判に出るとき、付き添って出廷することがあります。
嫌疑(けんぎ)
「この人が犯人かもしれない」と疑われている状態のことです。
まだ証拠が足りないけれど、調べる必要があるときによく使われます。
検察官(けんさつかん)
国家の立場から「被告人は有罪」と主張する人です。
事件の捜査や、起訴するかどうかの判断もします。
「検事」と同じ意味です。
※日本では、取り調べ担当の「捜査担当」と、裁判に出る「公判担当」で役割分担されています。
控訴(こうそ)
地方裁判所の判決に不服がある場合、上の裁判所に「やり直して」とお願いすることです。
次の裁判は高等裁判所で行われます。
高等裁判所(こうとうさいばんしょ)
地方裁判所の上にある裁判所です。
略して「高裁(こうさい)」
控訴された事件などを扱います。
口頭弁論(こうとうべんろん)
裁判で当事者どうしが主張を話す場面のことです。
民事事件では早口で専門用語が多く、傍聴していても分かりづらいことがあります。
公判前整理(こうはんまえ せいり)
裁判が始まる前に、証拠や争点を整理しておくための準備のことです。
これによって、裁判がスムーズに進みます。
裁判員制度でよく出てくる言葉です。
拘留(こうりゅう)
軽い罪に対して科される刑罰のひとつで、1日以上30日未満、刑務所などに入って過ごすものです。
あくまで「刑」なので、有罪判決が出たあとに行われます。
罪状(ざいじょう)
「どんな罪を犯したのか」を説明する言葉です。
裁判で読み上げられ、「罪状認否(ざいじょうにんぴ)」につながります。
罪状認否(ざいじょうにんぴ)
「あなたはこの罪を認めますか?」と聞かれる場面です。
公判の最初に行われ、被告人が答えます。
裁判員(さいばんいん)
重大な事件で、市民がくじで選ばれて参加します。
裁判官と一緒に判決を考えます。
また裁判員が参加して進められる裁判のことを「裁判員裁判」、この制度のことを「裁判員制度」といいます。
裁判官(さいばんかん)
裁判を進めて、最後に判決を出す人です。
事件によって1人や3人で担当します。
示談(じだん)
事件を起こした人と被害者が、裁判の前に話し合って問題を解決することです。
被害者がゆるす意思を見せた場合、起訴されなかったり、刑が軽くなったりすることもあります。
実刑(じっけい)
判決が出てすぐに刑務所に入る刑のことです。
執行猶予がつかず、刑がすぐ実行されます。
執行猶予(しっこうゆうよ)
「刑はあるけど、すぐには刑務所に行かなくていいよ」という意味です。
一定期間問題を起こさなければ、服役せずに済むこともあります。
釈放(しゃくほう)
逮捕や勾留されていた人を、手続きを経て自由にすることです。
不起訴になった時や、保釈された時も「釈放」と言います。
※「仮釈放(かりしゃくほう)」は刑務所にいる人が、刑の一部を終えた段階で外に出られる制度で、釈放とは対象者が違います。
収監(しゅうかん)
裁判で有罪が確定した人を、刑務所などに入れることです。
判決が出て「実刑」になった人は、このあと収監されます。
上告(じょうこく)
高等裁判所の判決に納得できない場合、最高裁判所に再び判断を求めることです。
ただし法律の解釈などに限られ、簡単には認められません。
証拠調べ(しょうこしらべ)
裁判の中で、証人の話を聞いたり、書類や映像を見たりして、証拠を確かめることです。
「この証拠が本当に正しいのか?」を検討する大切な場面です。
証拠不十分(しょうこ ふじゅうぶん)
罪を証明する材料(証拠)が足りないことです。
この場合は「無罪」となることもありますが、犯人ではないと確定したわけではありません。
証人尋問(しょうにんじんもん)
事件について知っている人に、裁判で話を聞くことです。
弁護士や検察官が順番に質問します。
書記官(しょきかん)
裁判の記録をとったり、スケジュールを管理したりする裁判所の職員です。
法廷で法衣を着て、パソコンに向かって入力している姿をよく見かけます。
書類送検(しょるいそうけん)
逮捕せずに、警察が事件の書類を検察に送ることです。
軽い事件や未成年の場合に多く見られます。
書類送検されても不起訴になれば前科はつきません。
心神喪失(しんしんそうしつ)
事件を起こしたときに、自分が何をしているか理解できない状態のことです。
この場合は「責任能力がない」と判断されて、刑罰は科されず無罪になることがあります。
※心神耗弱(しんしんこうじゃく)は、事件を起こしたときに、少し判断力が落ちていた状態のことです。責任能力はあるとされますが、刑が軽くなることがあります。
精神鑑定(せいしんかんてい)
被告人が事件を起こしたとき、自分の行動を正しく判断できたかどうかを、専門の医師が調べることです。
責任能力の有無によって、裁判の結果が大きく変わることがあります。
責任能力(せきにんのうりょく)
事件を起こしたときに、自分の行動が悪いことだと理解できる力のことです。
責任能力がないと、たとえ事件を起こしても刑事罰を受けないことがあります。
これは刑法第39条に基づいた考え方で、議論になることが多いです。
前科(ぜんか)
過去に罪を犯して、有罪判決を受けたことがある記録のことです。
裁判では、前科があると刑が重くなることがあります。
「前歴(ぜんれき)」=逮捕されたけど有罪になってない記録(警察内部の記録で公けには出ない)とは分けて使われます。
宣誓(せんせい)
証人が「うそを言いません」と誓うことです。
この宣誓のあとに証人尋問が始まります。
地方裁判所(ちほうさいばんしょ)
札幌地裁など、私たちが傍聴する刑事裁判の多くがここで行われます。
略して「地裁(ちさい)」
重大事件も扱う、裁判の中心的な場所です。
調書(ちょうしょ)
取り調べや証人の話などを記録した文書です。
「供述調書(きょうじゅつちょうしょ)」と呼ばれることもあり、裁判で読み上げられることがあります。
陪審員(ばいしんいん)
アメリカなどで使われている制度で、一般市民が裁判に参加し「有罪か無罪か」だけを判断します。
日本では現在は使われておらず、代わりに「裁判員制度」が行われています。
初公判(はつこうはん)
その事件で最初に開かれる裁判のことです。
事件の内容や、被告人の意見がはじめて明かされます。
事件によっては、初公判で判決まで進むこともあります。
判決(はんけつ)
裁判の最後に出される「結論」です。
有罪か無罪か、どんな刑にするかが決まります。
被告人(ひこくにん)
裁判で罪に問われている人のことです。
ニュースでは「被告」と略されることもあります。
※裁判が始まる前の、取り調べの段階では「被疑者(ひぎしゃ)」と呼びます。ニュースでは「容疑者」と使われます。
弁護人(べんごにん)
被告人の立場を守る弁護士さんです。
無罪や刑の軽さを主張します。
※国選弁護人=お金がない人のために、国がつけてくれる弁護士(重大事件でつくことが多い)
※私選弁護人=被告人や家族が自分で選んで依頼する弁護士
傍聴人(ぼうちょうにん)
裁判を見に来た一般の人のこと。
私たちが裁判所へ行って座ると、この立場になります。
保釈(ほしゃく)
被告人が裁判の間に家に帰れる制度のことです。
「逃げません」と約束して、お金(保釈金)を預ける必要があります。
民事裁判(みんじさいばん)
お金や契約などのトラブルを解決する裁判です。
刑事裁判と違い、検察官は関与しません。
無罪(むざい)
裁判の結果、「有罪とは言えない」と判断された状態のことです。
証拠が足りない、疑わしきは罰せず…などの理由で、有罪にできない場合に使われます。
「無実」とは裁判ではまったく違う意味を持ちます。
無実(むじつ)
そもそも犯罪をしていないこと。
「その人はやっていない」という事実をさしますが、裁判では無実でも無罪になるとは限りません。
黙秘権(もくひけん)
裁判や取り調べで、話したくないことを無理に答えさせられない権利です。
「黙っていること」も本人の大切な権利のひとつで、初公判のときに必ず裁判官から被告人に説明があります。
留置(りゅうち)
警察署に一時的にとどめておくことです。
逮捕された人を、取り調べなどが終わるまで警察の施設に置いておくときに使われます。
累犯(るいはん)
過去にも罪を犯したことがあり、また犯罪をしてしまった人のことです。
前科があると、同じ罪でも重く扱われることがあります。
刑務所に入るために、わざと累犯を重ねる人もいます。
論告求刑(ろんこくきゅうけい)
検察官が、「これまでの証拠から見て被告人は有罪だと思います。そして〇年の刑にすべきだと思います」と、事件の概要と意見をまとめて発表することです。
和解(わかい)
裁判をしている途中で、おたがいが話し合って納得できる形で争いを終わらせることです。
民事裁判でよく使われます。

むずかしく感じる裁判の言葉も、少し意味を知るだけでぐっとわかりやすくなります。
傍聴やニュースを見るときに、ぜひこの用語集を役立ててください。
今後も適宜、用語を追加していきます。


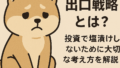
コメント