最近、クラウドソーシングやブログ運営において、生成AI(ChatGPTなど)を活用して記事を作成する人が増えています。
ですが、納品先によっては「コピペチェックを通過すること」が条件になっているケースも多く、「AIで書いた文章って本当に大丈夫なの?」と不安に思う人もいるのではないでしょうか。

自分でブログを書いて、収益化するときにも気をつけたいポイントですね。
そこで今回は、実際に生成AIで作成した教育ジャンルの記事を、無料のコピペチェックツールに通してみる実験を行いました。
目次
実験内容:某教育教材紹介記事を生成AIで作成
使用した題材は「進研ゼミ小学生講座の特徴」。
ChatGPTに600文字程度で要点をまとめてもらい、保護者向けの紹介記事を生成しました。

AIへの投げかけ「進研ゼミ小学生講座の特徴について、600字でまとめて」
生成AIが作成した文章
進研ゼミ小学講座は、ベネッセコーポレーションが提供する小学生向けの通信教育で、子ども一人ひとりの学習状況や興味に合わせた柔軟な学びを提供しています。
1. 学習スタイルの選択肢 「チャレンジタッチ」(タブレット学習)と「チャレンジ」(紙教材)の2つのスタイルから選べます。どちらも教科書に準拠しており、学校の授業と連動した学習が可能です。
2. 無学年学習とAI活用 AIを活用した「無学年学習」では、国語と算数の全学年分の内容に取り組めます。得意な分野は先取り、苦手な分野はさかのぼって学習することで、個々の理解度に応じた学びが実現します。
3. 個別指導と記述力の育成 担任制の「赤ペン先生」による月1回の添削指導で、記述力や思考力を養います。同じ先生が継続して指導することで、学習へのモチベーションも高まります。
4. 実力診断と復習ドリル 全国規模の実力診断テストを定期的に実施し、学力を客観的に把握。その結果に基づいた個別の復習ドリルで、苦手分野を効率的に克服できます。
5. 英語・プログラミング・読書の充実 受講費内で英語4技能(聞く・話す・読む・書く)やプログラミング的思考を学べます。また、電子図書館「まなびライブラリー」では約1,000冊の書籍が読み放題で、読解力や知的好奇心を育てます。
6. 学習習慣の定着サポート AIが提案する「MY学習プラン」で、日々の学習内容を明確化。さらに、学習の取り組みに応じてポイントがたまり、努力賞と交換できる仕組みで、子どものやる気を引き出します。
進研ゼミ小学講座は、基礎学力の定着から応用力の養成まで、幅広いニーズに対応した教材とサポート体制が整っています。自宅での学習を充実させたいご家庭にとって、効果的な選択肢となるでしょう。
判定結果:無料(DL必要なし)のコピペツール
無料ながら高精度と評判の「CopyContentDetector」にかけた結果は以下の通りです。

- 類似度判定:3%(良好)
- 一致率判定:18%(良好)
- テキスト間判定:0%(良好)
ChatGPTで作成した進研ゼミ紹介記事をCopyContentDetectorでチェックした結果
→ 類似度3%・一致率18%と、非常に良好な判定に!
このように、AI生成記事でも、コピペの疑いなく通過できることがわかりました。
試しに…他の人の記事をそのまま使ったら?
次に、ネット上の他のブロガーさんが書いた「進研ゼミ」の紹介文をそのままコピーして、同じツールでチェックしてみたところ…

- 類似度判定:78%(コピーの疑い)
- 一致率判定:86%(コピーの疑い)
ネットに掲載されている他人の紹介記事をそのまま使用した場合の結果
→ 類似度78%、一致率86%で“コピーの疑い”判定に…!
と、明確に「コピペ判定」されました。
この結果は当然ではあるものの、生成AIで書いたオリジナル風の記事と、単なる転載の違いが数値ではっきりと示された形です。
ツールによって精度には差がある
さらに同じ文章(コピペしたブロガー記事)を、別の無料チェッカーにかけたところ、すべて「一致なし」「問題なし」と判定されてしまいました。
同じ文章を別の無料チェッカーにかけた結果
→ すべて「一致なし」と判定されてしまう結果に…
ここではサービス名は伏せますが、コピペチェッカーにも精度の差があるということは理解しておくべきでしょう。
より正確に判定したい場合は、信頼できるツールを選ぶか、有料版の利用を検討するのが安全です。
【応用】質問の仕方を変えれば、記事の方向性も変わる
今回使ったプロンプトは「進研ゼミ小学生講座の特徴を600字でまとめて」というシンプルなものでした。
ですが、質問を少し変えるだけで、まったく違う切り口の記事を作ることも可能です。
例:「進研ゼミ小学生講座の特徴について、他の教材と悩んでいる親御さん向けに600字でまとめて」と聞いてみた結果
他の通信教材とどれを選ぶか悩んでいる保護者の方へ、「進研ゼミ小学生講座」は学力の定着から応用力までしっかり育てるバランスの良い教材です。
まず大きな特長は、学習スタイルが選べること。紙の「チャレンジ」とタブレットの「チャレンジタッチ」があり、お子さんの性格や学習習慣に合わせた形で取り組めます。特にチャレンジタッチでは、AIが一人ひとりの理解度に応じて最適な問題を出題するので、苦手克服や先取り学習がしやすくなっています。
また、担任制の「赤ペン先生」が毎月添削を行ってくれるのも魅力です。自分の答案を見てフィードバックをもらえることで、記述力や表現力がぐんと伸びます。紙教材では実際に手を動かして考える力が、デジタルでは視覚的に理解しやすい仕組みがそれぞれ活かされています。
さらに、定期的に行われる「実力診断テスト」で今の実力をチェックできるのも安心ポイント。テスト後は復習ドリルで苦手をしっかりカバーできるので、「やりっぱなし」にならず、学びが定着します。
加えて、英語やプログラミング、読書といった今の時代に求められる学びも、追加費用なしで取り組めるのは進研ゼミならでは。特に「まなびライブラリー」は1,000冊以上の本が読める電子図書館で、読解力を自然と育てられます。
「勉強習慣をつけさせたい」「なるべく一人で学んでほしい」という方には、毎日の学習をサポートするスケジュール機能や、頑張りに応じたごほうび制度も心強い味方です。
教材選びに迷っているなら、内容・サポート・続けやすさのバランスが取れた進研ゼミは、一度体験してみる価値があります。
同じ教材でも、切り口や読者ニーズに合わせて「質問の仕方」を工夫すれば、全く違うテイストの記事が作れるという好例です。

「悩みに寄り添うような優しい文体で」や「できるだけシンプルに電車の中でもサクッと読めるように」などと注文をつけると、また違う文章になります。
生成AIでライターの仕事はなくならない
今回の実験で、「生成AI=コピペになる」という誤解が少しでも払拭されると嬉しいです。
ただし、生成AIはあくまで「素材づくり」や「時短ツール」であって、 読者に刺さる記事に仕上げるには、人間の視点・問いかけ・構成力が不可欠です。
同じテーマでも、質問の仕方や切り口次第で、まったく違う興味深い記事に変わります。
つまり、生成AIをうまく使いこなせるライターこそが、今後求められる存在になるのだと思います。
生成AIで作成した画像をブログに使う場合はこちら
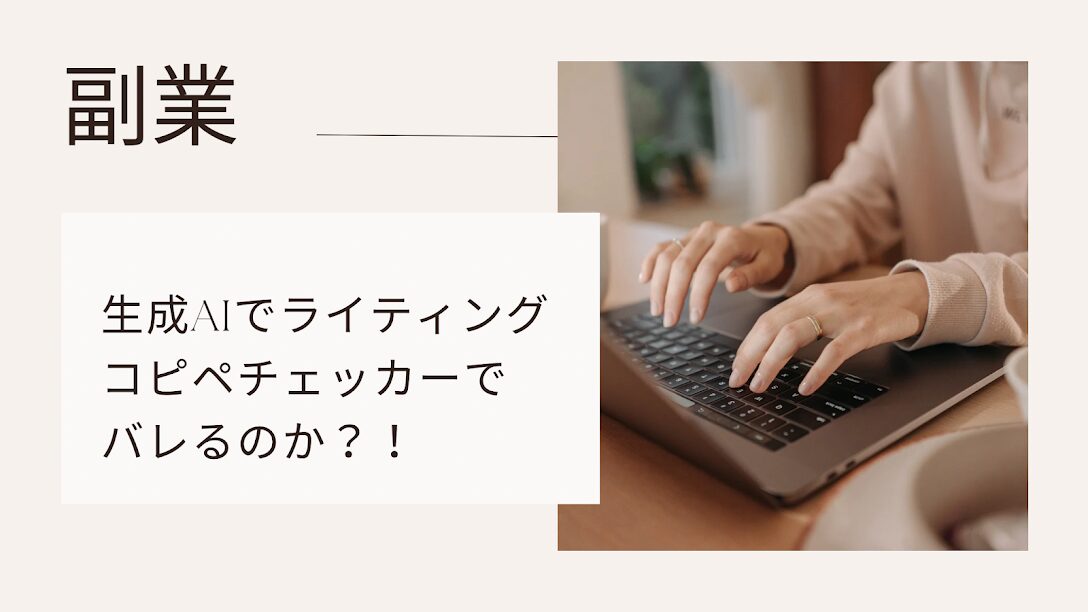



コメント