「またトイレ?」──その言葉がプレッシャーになることも・・・
「授業中に何度もトイレに行きたがる」
「休み時間でもトイレから出てこない」
「お腹が痛いと言って学校を休みたがる」
そんな子どもの様子に、親として戸惑うこともありますよね。
実はその多くが「心因性頻尿」と呼ばれる、不安や緊張が原因で起こる一時的な症状です。
身体に異常がなくても、「行けなかったらどうしよう」「漏れたら恥ずかしい」という思いが強くなると、脳が過敏になり、尿意を感じやすくなってしまうのです。
目次
子どもの心と身体で起きていること
学校での緊張やストレス
発表、テスト、先生や友達との関係など・・・
プレッシャーの多い環境では、「トイレに行けないかもしれない」という予期不安が強くなります。
特に進級やクラス替えなどで環境が変わったばかりの頃に起きやすいです。

昔のようにトイレを我慢させる教師は少なくなりましたが、それでも子供にとっては言いづらい環境に変わりありません。
「またトイレ?」と言われる経験
無意識に悪意なく言ってくる人もいます。
しかし言葉を受け取った方は、「我慢しなきゃ」「行ってはいけない」と感じてしまい、そのプレッシャーが尿意を強めてしまいます。
身体の緊張反応
そのほかにも様々な不安によって交感神経が活発になり、膀胱が刺激を受けやすくなる場面があります。これは子供に限った話ではないですよね。
さらに「トイレ=不安の象徴」のような思考パターンができてしまうと、「また行きたくなったらどうしよう」と思う頻度が増えていきます。これが心因性頻尿が長引いてしまう原因です。
大人よりも子どもの膀胱はとても小さいです。つまりおしっこを溜めておける量も少ないということ。
また言葉で意思表示ができる大人と違い、繊細な子ほど自分の不安を口にすることができません。子どもの心因性頻尿に向き合うには、そのことを十分に理解することからです。
こんなサインは心のSOSかも
- トイレに長くこもる
- 授業や行事の前に何度も行く
- 陰部がヒリヒリ痛むと訴える
- 「お腹が痛い」「気持ち悪い」と訴える
- 学校を行き渋るようになる
これは「サボり」ではなく、不安が身体の反応として出ているサインです。

一方で、遊んでいる時には全くトイレに行かないことがあるのも特徴です。
本人が抱えている不安を取り除くことが、症状改善の第一歩になります。
親ができるサポート法
①叱らずに安心を伝える
「また?」とつい言いたくなる気持ちもありますが、子どもは自分でもどうにもならない不安を抱えています。
「大丈夫だよ」「行っておいで」と受け止めるだけで、子どもの心はぐっと軽くなります。
またトイレに時間がかかることを急かすのもやめましょう。その子にとってトイレが安心基地になっている場合があります。
②いつでも行ける環境を整える
担任の先生に事情を伝え、トイレに行きやすい席やタイミングを相談しましょう。
「いつでも行ってもいい」という許可があるだけで、安心して授業に参加できるようになります。

特別な計らいを親が遠慮しないでください。将来に関わる大切な相談です。
「トイレに行くのは休み時間のみ」という考えを変えられない学校なら、転校してもいいと思っています。それくらいの覚悟をもって子供を守りましょう。
③拭き過ぎに注意する(特に女子)
トイレの回数が増えると、デリケートゾーンをゴシゴシ拭くことで粘膜が刺激を受けやすくなります。それが逆に尿意を誘発することも。
やさしく押さえるように拭き取り、おうちでは柔らかく刺激の少ないトイレットペーパーを選んであげましょう。
④備えは恥ずかしくないことを伝える
特別な備え(吸水パッドや下着)を「赤ちゃんみたいで嫌」と感じる子もいます。その気持ちは自然なことです。
でも今は、見た目が普通のパンツに見える吸水ショーツや、可愛い布ナプキンタイプの吸水パッドなど、誰にも気づかれない安心アイテムがたくさんあります。
特に布製のものは肌に優しくほんのり温かく感じるので、つけているだけでリラックス効果(いわゆるプラセボ効果)も期待できます。
⑤一緒に備え実験をしてみる
吸水パッドやショーツはどのくらい水を吸うのか?を、実際におうちで親子で水を垂らして試してみるのもおすすめです。
「こんなに吸うんだ!」という安心感が、不安の軽減につながります。
⑥声かけの工夫で安心を根づかせる
「トイレ行っておく?」という一言が、いつでも行っていいという安全信号になります。
親の中にはあえてトイレの話題に触れない人もいますが、日常的に伝えることで、子どもは「当たり前のルーティン」と思えるようになります。
やがて安心感が根づくと、自然とトイレの回数も落ち着いていきます。
頻尿対策で大切なのは、トイレを行く回数を訓練で減らすことではありません。
行きたい時に行ける安心感を持ってもらうこと、そしてもしもの時には備え(サニタリー用品の工夫)がちゃんと守ってくれることを、根気よく伝えることです。

トイレが近いは個性です
頻尿は、心が「ちょっと休みたい」と言っているサインかもしれません。その不安を理解して、受け止めて、安心できる環境を整えることが親としてできることです。
トイレに行きたくなるのは、心ががんばっている証拠です。「大丈夫だよ」と言ってもらえるだけで、子どもはまた前を向けます。
親は子どもが安心できる声がけと物理的な備えを、いくつか用意しておきましょう。
子どもの頻尿はほとんどが一時的で心因性のものですが、まれに膀胱炎・糖尿病・腎疾患などの身体的な病気が隠れている場合もあります。まずは必ず、小児科または泌尿器科を受診し、身体的な原因がないかを確認してください。
尿もれ対策がもっと当たり前にオープンになることを願って、様々な記事を投稿中です☟

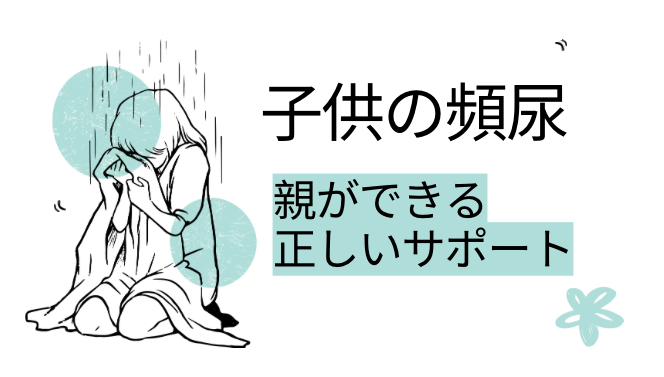


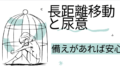

コメント