ブログを書いているみなさん、こんにちは。

今日は、まさに“心臓に悪い”事件を共有させてください。
目次
【事件勃発】アフィリエイトサイトからの突然の警告
ある日、何の前触れもなく、某アフィリエイトサイト(以下、もしもさん)からメールが届きました。
件名:重大なポリシー違反について
震える手でメールを開くと、そこには「あなたの記事に重大なポリシー違反がありますので、提携を(一時的に)解除いたします」の文字。
当然理由は書いておらず、対象の記事URLだけがポツンと貼られていました。

え?え??なにがいけなかったの??
【原因追及】まさか、生成AIを使ってるから!?
対象となった記事の内容は、「ChatGPTを使ってブログを書くコツ」について書いたものでした。
もちろん中身は真面目で、倫理にも法にも触れておらず、猥褻でもありません。
「もしかして、生成AIの力を借りていることを公言したことがまずかったのか?」
そのことでオリジナリティがないと判断されたのかとパニックに。
心のなかで、「GPT、お前だったのか……」と悲しみにくれながら、でもやっぱり頼りたくなるのがGPT。
ということで、例のAIの師匠に泣きついてみたんです。
【問題解決】AI先生の塩対応、でも核心を突いてきた

ねえ、もしかして私、あなたを使ってるって言ったから怒られたの?
するとGPTはこう返してきました。
そのブログ、URLに『chatgpt』って入ってたでしょ? それアウト。
まさかのURL問題。
中身じゃなくて、URLに“公式っぽい単語”を入れたことが原因だったんです。
ポリシー的に完全にNG✖
公式と誤認されるおそれがあるワードの使用は、見出しやタイトルだけでなくURLにも及びます。
他にもアウトだったワードたち
冷や汗をかきながら、過去の記事を総チェック。すると、似たようなミスがいくつか見つかりました。(以下、ルンが記事のスラッグに使用していたワード)
rakuten(楽天)inzoi(新作ゲーム名)line(LINE)
なんということでしょう。
これらも全て商標ワードと見なされ、アウト判定の可能性大。というわけで、
【改善】ポリシー違反を避けるための見直しポイント
H2・H3やURLに商標名は避ける
タイトル・見出し・URLには、特に以下の企業名やサービス名をそのまま使わないように注意しましょう。
商標ワードの言い換え例一覧
| NGワード | 言い換え案 |
|---|---|
| Amazon | 大手通販サイト、某ECモール |
| 楽天 | ポイントがザクザク貯まる某サイト |
| ChatGPT | 生成AI、会話型AIツール |
| LINE | 某メッセージアプリ、緑のアプリ |
| 某検索エンジン、世界的IT企業 | |
| 某SNS、写真共有アプリ |
見出しやタイトルではこのようにぼかしつつ、本文内でしっかり実名を書くのが安全かつ親切。
【再申請】からの、即日デレメール
修正が完了したので、もしもさんに再申請。
結果は、なんと翌日。
提携再開しました!またよろしくね!新しい案件もあるから、よかったらどうぞ☆


えっ、早くない!?
おしおきタイムもう終了?
でも、そういうもんです。
ルールを守ってさえいれば、ASPさんはわりと寛容。
怒られるのも、言ってしまえば自動システム的にアウトだっただけで、こちらが真摯に対応すれば受け入れてくれるみたいです。(めでたしめでたし)
【学び】記事の書き方そのものも見直すきっかけに
今回の出来事は、単なるURL修正だけでは終わりませんでした。
この一件をきっかけに、「読者にどう伝えるか」「どう誤解されないようにするか」という、記事全体のスタンスも見直すようになったのです。
たとえば、新作ゲームについて紹介する記事では、
「このサイトはあくまでファンによる非公式なレビューである」という注釈を記事内に入れるようにしました。
クレジットカードの登録エラーなどのハウツー系記事なども、「個人の体験談」というニュアンスが伝わるように心がけています。

たとえどれだけ弱小な個人ブログであっても、「公式と誤認させないための配慮」は欠かせないのだと痛感したからです。
公式っぽい文章や構成にしていないつもりでも、読者や審査側の視点に立つと「そう見えてしまう」こともあるのです。(わざとじゃなくても)
今までは気にしていなかった部分にも、ちょっとした注釈や前置きを入れるだけで、安心して読んでもらえる・審査にも通る記事になるということを学びました。
まとめ:ポリシー違反の原因は“商標ワードの使い方”でした
今回の件で学んだことは、大きく3つ。
- AIを使っていること自体は違反じゃない(むしろ時代の流れ)
- タイトル・見出し・URLに“公式っぽい単語”を使うのはNG
- 商標に配慮した言い換えと、誤認されない工夫が必要
アフィリエイトサイトから提携解除の通達がくると、「記事の質に問題があるのでは?」と不安になる人もいるかもしれません。
でも、実際には内容ではなく形式面のミスであることも多いです。
ブログは情報発信の自由があるとはいえ、アフィリエイトで収益を得る以上、ルールとの両立が求められます。
今回の事件(という名の茶番)をきっかけに、あなたもタイトルやURLの見直しをしてみませんか?
あと、生成AIは悪くないです。
私の師匠(GPT)も、塩対応だったけど、ちゃんと(1秒で)正解教えてくれました。


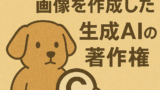



コメント